講座1オーガニック
⑤ 予防原則 -残留農薬問題に答える
ひところ話題になった農薬グリホサート(商品名ラウンドアップ)残留の問題。 小麦に関わる者として知っておきたいことです。 これを考える上で、「予防原則」が大事であるというお話を、澤登早苗先生(恵泉女学園大学)にしていただきます。 (文・池田浩明 、 囲み・「小麦の教室」事務局)
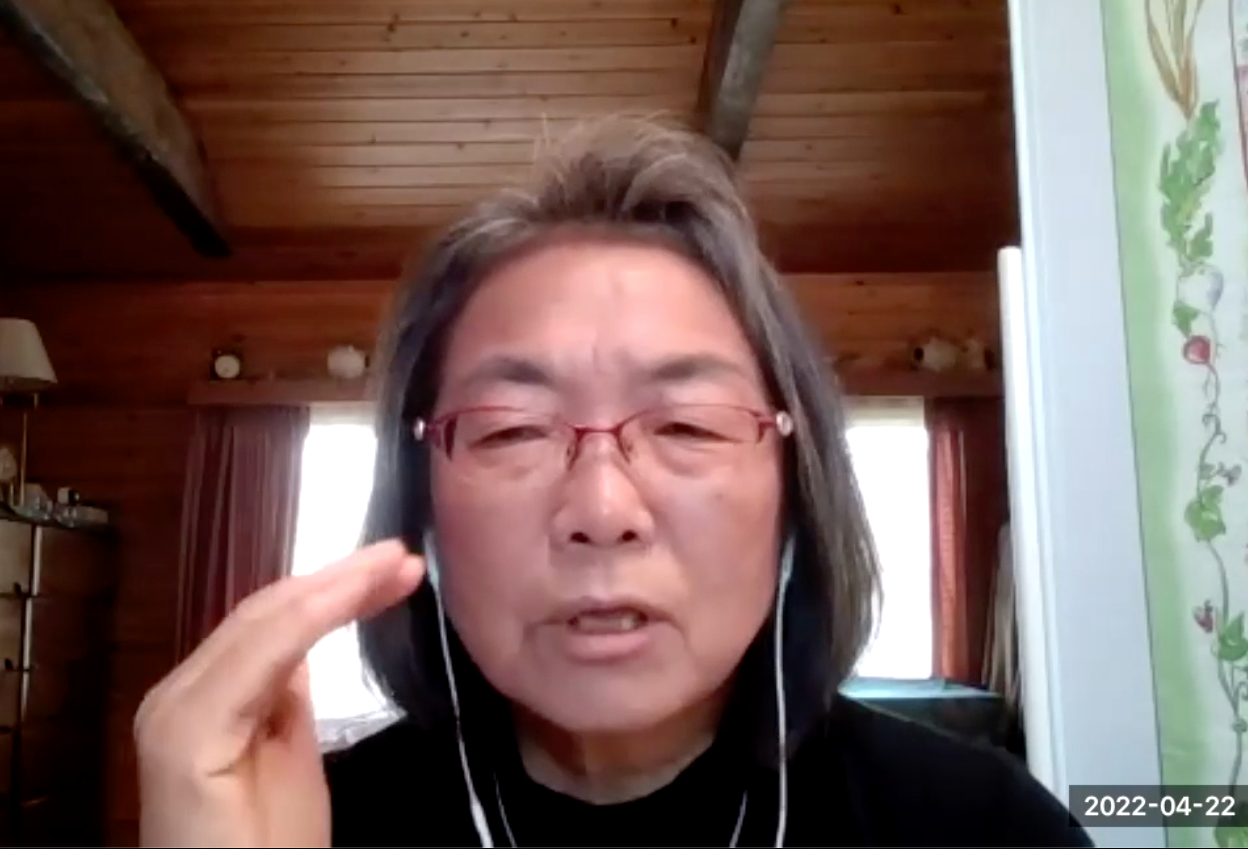
「小麦の教室」の動画版「なぜ有機小麦は増やす必要があるのか?」での澤登先生。
動画版をご覧になりたい方は、https://komuginokyousitsu1.peatix.com/ こちらにお申し込みください。
新麦コレクションの会員の方は、無料です。
小麦に関わる人は知っておきたい
グリホサート残留の問題
2019年4月、ある市民団体の調査が話題を呼びました。 13種類の食パン(ホールセールのもの)を分析したところ9種類からグリホサートが検出されたのです(国の定めた基準値は下回る)。 国産小麦を使用した4種類からは検出されなかったことで、外国産小麦の安全性がクローズアップされることになりました。
そもそもグリホサートとは除草剤のこと。 植物の中でアミノ酸が作りだされることを阻害して、雑草を育たなくしてしまうのです。 「非選択性」といってどんな植物にも効果があるため、生産者にとってはとても便利な除草剤。 国内でも使用されており、小麦生産の現場では、種まきの前に土壌に散布して雑草が育つことを予防する、といった使い方をするそうです。 ですから、作物に直接かかるということはありません。 ところが、一部の海外の小麦生産者には、収穫前にグリホサートを直接散布し、小麦を早めに枯れ上がらせるために使う場合があり(通常、収穫は自然に枯れるのを待って行う)、これが北米産の小麦からグリホサートの検出例が多いことの理由だと言われています。

