2020年1月号のメニュー 1 『nichinichi川島の上手いこと言っちゃって♡』第5回 川島善行 2 『ベッカライ コンディトライ ヒダカの四季』第6回「12月 シュトレン」 日高晃作 3 『日々之精進』第14回 橘和良(カドヤ食堂) 4 『武蔵野スローフード宣言!』第24回 岩澤正和(ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ オーナー) 5 『守ることと変えること』第6回「続・ワタシと補助金」 廣瀬敬一郎(大地堂) 6 『表紙の話』第1回 前田茂雄(前田農産) 池田浩明(パンラボ) *記事内容は、2020年1月時点のものです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「nichinichi川島の上手いこと言っちゃって♡」第5回 by 川島善行
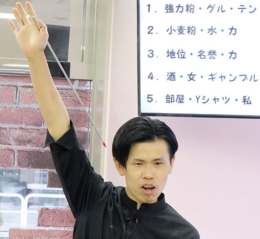
「ベンチタイム」 皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 あけおめ!ことよろ!と言う事で今回のテーマはベンタイです。 ベンタイこと、パン業界では知らない人はいないベンチタイムですが、ざっくり言うと分割やまるめをした生地を休ませて成形をスムーズに行う、生地にとっての休み時間のことです。 (パンによりますが)ベンチタイムを取るか取らないかで成形時の生地が言うことを聞いてくれるかどうか、全然違ってくるんですね。 凄いですね~! ベンチタイム!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「ベッカライ コンディトライ ヒダカの四季」 by 日高晃作 第6回「12月 シュトレン」 4月に食べられると質がよい 12月といえばドイツを代表するクリスマス発酵菓子「シュトレン」。 配合的にはリッチなフルーツパンといった感じなのだが、驚異的な賞味期限を誇る。時間を置くと味わい食感が変わってゆき、「4月イースターの時期に食べておいしければ、良いシュトレンだ」とドイツで教わった。1kgサイズがスタンダードであるドイツのシュトレンはその変化を味わえるが、原材料が高い日本ではそうはいかない。

採石場で寝かせる シュトレンを炭鉱跡で数か月間寝かせてから売り出すお店がドイツにあるのを聞いたことがある。いつか日本でもできないかと思っていた。大田市に、室町時代から採石の歴史を持つ、福光石の石切り場が今も稼働している。足を踏み入れると圧倒的な地中空間が広がっている。夏場でも20℃を下回る。歴史の香りを頂きながら、この一角にシュトレンを保管させてもらっている。世界遺産に指定された石見銀山の坑道跡でもいつか実現させたい。

先日やっと福光石の石切場より取り出してきました。歴史の香りを頂きながら、温度の安定した地中空間にゆっくり寝かせてきました」



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー カドヤ食堂・橘和良の 「日々是精進」 第14回「売り上げが1/3になって見えたもの」 ●10年目の危機感 カドヤ食堂をはじめて19年になります。 鶴見区の小さな店で創業し、10年前、いまの西区の店に移転。 厨房を広くし、シンクをたくさん備えて、仕込みに重きを置いた作りの店です。 オープン初日、300~400人ものお客様がお店に来てくださいました。 ところが、半年後の12月、寒くなってラーメンが恋しくなる季節なのに、売り上げが1/3になっていたんです。 それまでずっと、おいしいもの作ればお客さんは来てくれると思い込んでいたのですが、そのときは潰れるかもしれないと危機感が出ました。 ●商品がわかる人をホールに置くと強い 10年前といえば、口コミサイトが盛んになってきた頃。 はじめて覗いてみました。 いいことを書いてくださってる人もいましたが、よろしくない書き込みも多かった。 明らかに悪意のある書き込みもあれば、嫌な思いをしたという悲痛な書き込みもある。 読ませてもらって、はっと気づきました。 作ること、仕込みばっかりに力を入れるあまり、商品知識がない新規のパートさんをホールに入れてしまい、接客がまったくなってなかったんです。 創業の店は小さかったので、対面でラーメンを渡してました。 店が大きくなり、僕の見えないところでやりとりをしていたのです。 製造がわかる子をホールにまわそう。 当時は、いまは独立した右腕・左腕がいた。 中のことがわかる店長クラス。 商品の説明もきちんとできるし、中でちょっとした行き違いがあっても上手くリカバリーできる。 商品のことがわかる人をホールに持っていくと、いちばん強いです。 それでも一回落ちた信用を回復するのはほんまに時間がかかりました。 接客はいちばん大事。 味の好みはいろいろあります。 こってりなラーメンが好きなお客さんは、うちの味はあわないかもしれない。 でも、接客は人として当たり前のこと。 みなさん、わざわざうちの店を選んで来てくださってる。 接客は極力丁寧にやるよう心がけています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 武蔵野スローフード宣言! by 岩澤正和(ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ オーナー) 第24回 「練馬大根」

●練馬大根に客がついた
そして自分が練馬大根と向き合ってから数年
ここのところお客様の考え方が変わってきたなって手ごたえがあります
イタリアンで大根はほとんど使われませんが
今ではサラダはもちろん
伝統のパスタやピッツァやジェラートにも使っています
みんな干したり熟成させたりと古くからの知恵を利用したメニューです
はじめは「大根」って鼻で笑われることが沢山あって
自分でも面白半分で料理を試行錯誤
ですが最近はみんな否定をしないで
わざわざ大根のメニューをこの時期食べに来るようになったんです
意外と驚きで
でもこれなんですよね本質は
●スタッフが風邪を引かない
今は毎日賄いや味見で食べてますが
そんな先人の知恵の食材を当たり前に毎日口にすると
当たり前に地元の産物と向き合うと
医学的には解明できていないもしくは偶然かもしれませんが
自分も含め従業員全員今年風邪ひいてないんです
それがこれからの時代のヒントや答えなのかもしれませんね
地方の農家さんのところに行くとそんな食材が沢山眠ってて
本当に日本はもったいない
まだまだやれることはたくさんあるんだなと思います
少し便利になってしまい今まであった当たり前がなくなっています
今年はそこを強化します
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Mr.ディンケルの生産者コラム
「守ることと変えること」
by 廣瀬敬一郎(大地堂)
第6回「続・ワタシと補助金」
●補助金の中身を見てみよう
前回、小麦の生産が、補助金なしに立ちいかないことを、医療費を例にお話ししました。
今回はそのつづきとして、補助金の中身について、説明したいと思います。
小麦を作ると、10a(=1000m2=1反)あたり51400円(人件費6000円含む)の赤字が出ます。
補助金(税金)は、生産者の経営を維持するため、赤字を補填し、利益を確保させるお金です。
滋賀県日野町の農林61号240kg(10a[=1000m2=1反]の平均収量)に対する補助金。
対象補助金は4つあります。
1水田活用の直接支払交付金:35000円
2営農継続支払 :20000円
3数量払 :6700円
4産地交付金 :5000円
合計:66700円
ここから、赤字の額である51400円(人件費6000円含む)を引くと、10aあたりの利益は15300円となります。
上記3の補助金は、収穫量により変動いたします。
また、上記1~4の補助金額は麦に対してであり、その他の作物を栽培した場合は、上記補助金額ではございません。
2・3の補助金は、輸入小麦にかかっているマークアップ(政府が外麦を輸入する際、国産麦との差額を販売価格に含めて徴収しているお金)が財源としてあてられています。
ですが、マークアップはTPPや日米貿易協定により9年目までに45%削減され、減少分は国費で補う方針のようです。
●穀物に補助金が出る理由
米以外の作物(麦・大豆・WCS用稲・飼料用米・米粉用米・蕎麦)にもそれぞれ補助金額が決まっており、米と同等程度の収益を得られるようにしています。米の余剰作付をなくすことで、米価を安定させて農家所得を維持するための政策です。
平成30年 水稲作付面積 147万ha
麦類作付面積 27万2900ha
大豆類作付面積 18万4020ha
WCS用稲作付面積 4万2545ha
飼料用米作付面積 7万9535ha
蕎麦作付面積 6万3900ha
ワタシが農業を始めた2000年には、家畜用の餌であるWCS用稲(牛用)や飼料用米(豚・鶏用)はありませんでした。
米の消費量が年々減少する中、麦・大豆が作付できない地域や家畜の自給率を上げるという名目で、食用以外の選択肢を追加したのです。
生産者であるワタシが言うのもなんですが、食糧安保・食糧自給率・フードマイレージの観点からもこのような補助金は必要だと思います。
納税者(消費者)の皆さんに、正しく理解していただかないと成り立っていきません。
みなさんに広く知ってもらう努力をしていかないと。
●「日本は補助金が多い」は本当か?
補助金には、地域差(たとえば、滋賀県と北海道では異なっています)や個人差(栽培面積のちがいなど)があり、一概にダメだと判断できません。
ただ、「日本は補助金が多い」という議論がよく聞かれますが、それは本当でしょうか?
農業所得に公的助成が占める割合のデータ(2013年)です。
スイス 100%
フランス 95%
イギリス 91%
大地堂ひろせ 16%
これは、国の考え方や国民性が数字に表れた結果といえるでしょう。(つづく)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
表紙の話 第1回
前田農産・前田茂雄さんに訊く
「雪の降らない十勝」

十勝は、史上稀に見る雪の少ない冬を迎えています。 去年も少なかったが、もっと少ない。 畑も小麦が見えてるところがいっぱいあります(1/14現在)。 この分だと寒さと冷たいからっ風で枯れてしまうかもしれません。 9月に種をまいた秋まき小麦は冬のあいだ雪に覆われることで、布団かわりになり、寒さから守られます。 ですが、その布団がないため、寒さ丸出しです。 表面に出ている葉っぱは凍って、枯れる可能性がある。 せっかく降った雪も、日中は2℃まで上がるので溶けちゃうし、朝晩は-15℃にもなるので、しばれちゃう(凍っちゃう)。 いつもの年は、雪がバリアになって凍りにくくなるんだけど、雪がないと土壌の凍結が深くなりすぎてなかなか溶けず、春が遅れちゃう。 これで不作になるかどうかはまだわからないが、昨年10月以降に、遅めに種をまいた人は越冬前の体つくりが弱く春先の立ち上がりも心配です。 4月には土壌凍結が取れて根が活発に動きだす起生期に入ります。 正に、くたびれてた葉がピンっ! と立って生き生きてするシーズン。 心配と楽しみが入り混じる冬を過ごしてます。 *新麦新聞は、メールマガジンとして、2017年3月から毎月、NPO法人新麦コレクションの会員へ贈られていました。その時、表紙を作成しメルマガに付けていました。この号から、時々、表紙の話を掲載しています。

